柳先輩は、いつもかっこよくて優しくて、素敵な人。 赤也君が入ってるテニス部の先輩で、強いらしい。 平凡な私は結局見ているしかなくて こうして、ただ見ているしかなくて。 ≪憧れの痛み≫ 「なーにやってんだよ!」 ごつっと頭に何かがあたって鈍い痛みを感じた。 頭を摩りながら振り向くと、赤也君が笑いながら右手に辞書を持っていた。 どうやら私はあれで殴られたらしい。 女の子の頭を殴るなんてひどいじゃないか。 「悪魔の笑顔だ」 泣きそうな顔をすれば、ごめんごめんと少しだけ焦ったように謝る赤也君。 謝るなら最初からやらなければいいのに。 そもそも殴ったら痛いってことくらいわかると思うんだ。普通。 「赤也君が辞書持ってるなんて珍しいね」 「あぁこれね、柳先輩に借りたっつーか押し付けられたっつーか」 またテストの点数でも落ちたんだろうか。 めんどくさそうな声を出している赤也君の肩を頑張れと叩く。 柳先輩の辞書は、きっと色々と書き込まれているのかもしれない。 そんな辞書を赤也君に貸してくれるなんて 赤也君は柳先輩に近い所にいるんだなぁなんて思ったら、やっぱり羨ましくて。 「で、何してんの?」 「別に、何でもないけど」 ずっと柳先輩を見るために屋上から下を覗いていたなんて言ったらきっとまた笑われる。 というか引かれてもおかしくはない。 しかし、今日は遅いと思っていたら赤也君に辞書を渡していたのか。 「あれ、柳先輩じゃん」 「え、嘘、どこ?」 赤也君が下を見ながらそう言うから、思わず自分も身を乗り出して下を見ていた。 けれど、どれだけ見ても柳先輩はいなくて。 「嘘」 左を見れば赤也君がべっと舌を出している。 それは楽しそうな顔で、謀られたんだとわかった。 「お前柳先輩の名前出すと顔変わるんだもん。わかりやすすぎ」 「…そんなにわかりやすいかな」 わかりやすすぎて嫌になるくらいだなんて言ってべしべしと私の頭を叩く。 一体私は今日何回頭を叩かれたらいいのだろうか。 困りながら頭を抱えて守っていると、ため息と一緒に手が止まって そのままぐいっと頭を引っ張られた。 シャツが顔に当たって、その向こうの体温も顔に感じて 何が起きたかとよくわからなくてきょとんとして。 「どうしたの」 「少しは驚けよ」 苦笑いが聞こえる。 つまんねーなーなんて言いながらさっきまで叩いていた私の頭を優しく撫でる。 「赤也君変だよ」 「…これから言うことで泣くんじゃねーぞ」 「なに」 私が言い終わらない内に、被せるように聞こえた言葉。 それは大きくないはずなのに、私の頭を支配して。 「柳先輩に彼女できたから」 何も言えなくて、何も聞けなくて ゆっくりと思い出していく今までの記憶の中に、理由があった気がして。 涙は出なかった。 ただ、ぽっかり穴が空いた気がした。 「それってさ、何か有名な人だよね」 「知ってんの?」 「いつも、ここからよく見えるもん」 きっと柳先輩がこの時間に外に出ていたのは 彼女を見るためなのかもしれない。 そんなことも気付かずに、私はずっと柳先輩を見て、それで満足していて。 あぁ、だから今日は出てこないのかもしれない。 こんな所へ来なくても、先輩はその人に会いにいけるのだから。 「確か最近も賞取ったんだよね」 「俺はよく知らねえ」 興味ねえしなんて言葉がついてきて、赤也君らしいなと苦笑い。 やっぱり柳先輩が好きになるような人は 私みたいな平凡な人じゃなくて あんな風に人を魅了できる素敵な女性なんだなぁと思った。 「泣かないよ、私」 「お前って感情表現薄くねぇか?」 「そんなことないと思うけど」 まぁ、確かにあの人よりはきっと感情豊かじゃないかもしれない。 だからこそ、柳先輩は私になんて気付かないんだ。 私は影が薄いのかもしれない。 存在感もほとんどないのかもしれない。 活発でもないし。 どうしよう、自己嫌悪しか出て来なくなっちゃうな。 比べたってどうしようもないのに。 「私、憧れてただけだからさ」 「憧れ?」 「そう、好きだったわけじゃないから」 強がりを言った。 そう言うしかなかった。 そうしないと自分が潰れそうだった。 「別に気付いてくれなくたって、見てるだけでよかったんだもん」 「そうかよ」 「そうだよ。だから悲しくなんてないんだよ」 悲しくないよ。 それより、何か寂しいや。 だから好きなんかじゃないんだよ。 「俺は、ちゃんと気付いてるからな」 ぽつりと聞こえた呟きに、小さくありがとうと返す。 大丈夫だよ、そんなに心配しなくても。 大丈夫だよ、そんなに優しくしなくても。 これは憧れだから。 恋なんかじゃないから。 悲しくなんてないから。 苦しくなんてないから。 痛みなんて、いつかきっと消えるから。 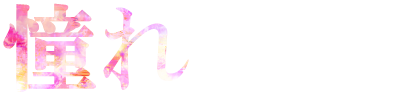
|