それは幼馴染の誕生日、午後5時のこと。 いつも夜の7時頃に呼び出すのに その主役は、準備も終わらぬ居間に来て、私に声をかけた。 「ちょっとついて来いよ」 「いいけど、準備どうすんの?」 「そんなの親にやらせろよ」 「えぇー…」 いつもいつも一緒の幼馴染。 それ以上でもそれ以下でもない、ただの幼馴染。 昔からずっと好きでいるのは私だけ。 あの日交わそうとした約束を覚えているのもきっと、私だけ。 ≪止まった時間を動かして≫ 「ちょっと時間あるな。お前、どっか行きたいところあるか?」 「じゃあ、お腹減ったから何か食べたいな」 「ならそこの店入るか」 適当に見つけた喫茶店に入って、何を食べようかなんてメニューを開く。 毎年誕生日を祝うのが当たり前になっていて 私はお昼から誠の家で誠のお母さんと一緒に準備を始める。 なのに、何で突然呼び出されたのやら。 「で、どうしたの?」 「何が?出かけんのはいつものことだろ」 「そうだけど。でも誕生日はいつも家にいるじゃない」 私の言葉にぶっきらぼうに「いいんだよ」とだけ答えて 真面目な顔でメニューを選び始める。 もしかしてお母さんと喧嘩でもしたのだろうかと少しだけ疑いながら 私も適当にメニューを選ぶ。 注文してから待つ間も、お皿が来てから食べ終わるまでも 絶対に誕生日の話だけは触れさせてくれなくて 私もとうとう折れて聞くのをやめた。 「あー、お昼食べてなかったから助かったー」 「食えよ、昼飯くらい」 「あはは、気付いたらこんな時間だったんだもん。 誠のお母さんも多分忘れてると思うよ」 笑い飛ばすと、誠が呆れた顔をする。 私も誠のお母さんも、誠を祝うことで頭がいっぱいだったのだ。 せっかくの18歳の誕生日。 もしかしたら、大学が離れてからはできないかもしれないから。 一緒に祝えるのだって最後かもしれない誕生日だから。 「それで、次どうする?もう日も暮れるけど」 といっても、今帰って夕飯とケーキなんてとても食べられそうにないけれど。 「お前、昔遊んだ公園って覚えてるか?」 「もちろん覚えてるよ。毎日のように行ってたもんね」 「あそこ行こうぜ」 少しだけ真面目な顔の誠にどきりとする。 思い出巡りでもするつもりだろうか。 何だかそれだと本当に最後みたいで嫌だけど。 「本当、どうしたの?」 歩きながら、そう聞いた。 「何でもねえよ」なんて誠は言うけど それこそ18年、一緒にいたんだ。 何でもなくないことくらい、顔を見ればわかる。 やっぱり、ずっと仲良く傍にいたいなんて 私だけなのかもしれない。 もしかしたら、私が誕生日に家に行って準備してることを 誠はどこかで嫌がっていたのかもしれない。 そんなことを考え始めたら止まらなくなって どんどん不安になってきてしまう。 「ついたな」 「懐かしいね」 「そうだな」 頭を振ってマイナス思考を投げ捨てて 昔よく遊んだシーソーに座り込む。 「ここすっごい覚えてる。 誠にいっぱい意地悪されたんだよ」 「それは覚えてるんじゃなくて根に持ってるんだろ」 「あはは、正解」 あの時は本当に痛かったんだからなんて言うと 「もっかいやるか?」なんてシーソーの反対側に誠の手がかかる。 「やだよ!本当にお尻痛いんだから!」 「そんなに痛いかよ」 「誠も一回体験してみたらいいんだよ!!」 ほらほらとシーソーを叩くと、楽しそうに誠が笑って 「変わんねえな、お前」 それが夕陽に照らされて、すごくかっこよく見えて。 思えば、誠は成長したんだと思う。 身長も高くなって、声も低くなって 力もついて『男の人』になった。 「…これでも私だって、成長したんだけどなぁ」 「知ってる」 誠が私の正面に立って、突然私の手を取って 私はびっくりして固まって。 「…何?」 「あんまり変わられても困るんだけどな」 その言葉の意味はわからなくて 私はただ、触れる手にドキドキするだけで。 その手の取り方に、小さく期待をするあの約束のこと。 だけどきっと、誠は覚えてないんだと思ってる。 それとも、子供の約束だからって無かったことにされてるのかもしれないなんて。 どこかで期待して、どこかで諦めてるあの約束。 ―――男の人ってさ ぽつりと聞こえた言葉に顔をあげる。 幻聴?記憶と重なってそう聞こえただけ? そんなことを考えてたら、誠がふっと笑う。 「男って、18で結婚できるんだってよ」 「知ってる。それ私が言ったんだもん」 「じゃあその時俺が何言ったか覚えてるか?」 覚えてるよ。 嬉しかったもん。 今だって。 「…誠が覚えてるなら、覚えてるかもね」 たまたま近くの駄菓子屋でやったクジ。 誠が当てたのはおもちゃの指輪。 私はそれを見て、何だかすごくうらやましくて。 ―――男の人ってさ、18才でケッコンできるんだって。 ―――ふーん ―――そのときにね、女の子の左手のくすりゆびにゆびわをはめて しあわせにするってやくそくするんだよ。 ―――じゃあ、そのときくる?おれのおヨメさん ―――え、いいの!? そうしたら誠がおもちゃの指輪を取り出して 約束するよって、私の薬指にはめようとして。 だけどタイミングよく夕焼けのチャイムが鳴って、お母さん達が迎えに来て 結局、そのまま手は離れて、指輪も約束も、全部小さいまま。 「今日は、迎えは来ねえよ」 「え…――」 その言葉に驚いてると指に触れた冷たい感覚。 手を見れば、指に通るその銀のリング。 そして、耳に響くのは胸の鼓動と、あの日と同じ夕焼けのチャイム。 昔と重なって進んだ今に、びっくりしてただドキドキして、見つめる左手。 「って…これ本物!?」 「そうだよ。びっくりしただろ」 「びっくりするよ!どうしたのこれ」 「言っただろ、18でお前を嫁にするって。だから、買った」 「か、買ったって…」 そんな簡単に高校生に買えるものなんだろうか。 私はそういうお店にあまり行かないのでよくわからないのだけど そんなこと考えて困惑してると、誠が少しだけ不満そうな顔をして。 「何だよ。いらねえのかよ」 「い、いる!ありがとう!」 慌てて返事をすると、誠がニッと嬉しそうに笑う。 でもこれって、婚約したことになるんだろうか。 私達まだ付き合ってもいないのに、いいのかな。 それとも、昔のままごとの続きなのかな…? 「」 「え?」 呼ばれて見上げた瞬間、触れた唇に驚いて。 「誓いの、な」 もう何も言えなくて、ただ顔が熱くなる。 黙って頷いて、優しく抱きしめられたまま誠に寄りかかる。 覚えていてくれるなんて思ってもみなかった。 あの日の続きがあるなんて思ってなかった。 好きなのは、私だけだと思ってた。 それに、たとえ、それが現実に起こったとしても 本当に18で迎えに来てくれるなんて思わなかった。 「あ、そうだ…」 「何だよ」 これからもまた 毎年、君を祝えることができるから。 「誕生日、おめでとう」 ずっと、隣で。 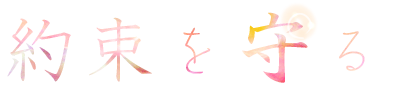
|